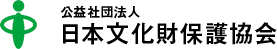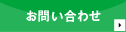堀木真美子 (公益財団法人愛知県教育・スポーツ振興財団 愛知県埋蔵文化財センター)
DX推進委員の堀木です。
愛知県埋蔵文化財センターでは、2009年頃から発掘調査データのデジタル化を順次進めてきました。フィルムカメラからデジタルカメラへの移行をはじめとして、遺構図面や調査日誌などもWebを活用することを前提にデジタル化を進めてきました。現在では、調査日誌をはじめとしてすべての記録がデジタルで格納する「電子納品」となっています。この「電子納品」は当センターの「基本マニュアル」で規定しています。ここでは、図面類のレイヤー分けや線種の指定の他に、フォルダーやファイル名の付け方を指定しています。
「電子納品」をはじめて十数年がたちますが、問題点も見えてきました。今回はそのうちの2つについてお話します。まず、図面類のプレビューができないことで、データベースの格納に時間がかかってしまう点です。電子化されたデータについて、ファイル名やテキスト、画像については、標準化されたもので集約していますので、圧縮するのも整理するのも簡単なので、Webデータベースへの登録は簡単です。ただし遺構図面類は、ちょっと困りものです。遺構図面類は、調査区全体の遺構の配置や、土層断面図、遺物の出土状態図などで、ファイル形式はDXFを基本としています。DXFファイルは、多くのCADソフトで活用が可能なので、この形式を採用しています。ところが、DXFファイルは、Webブラウザーで表示することができません。そのため、ファイルの内容を確認するだけでも、いちいちファイルをダウンロードしないといけません。その手間を省くためにDXFファイルのプレビュー画面を作成しますが、この作業が思いのほか時間がかかってしまい、データベースへの登録が遅くなっています。
もう一つは、データベースに格納される前のデータについて、職員が勝手に創意工夫をしてフォルダーを増やしてしまう問題です。これは、規定しているファイル名が人間にとってわかりにくい(半角英数字しか使用できない)ことから、例えば複数ある調査区毎にフォルダーを作成してデータをまとめてしまうというものです。多くの場合、新規のフォルダーをなくすことで、従来の形に戻すことができますので、大きな問題にはなりませんが・・・。フォルダーを増やしてしまうと、機械的にデータベースへの流し込みができなくなるのと、フォルダーごとで同一のファイル名ができやすくなりデータベース的には大変困ることになります。当センターの「電子納品」は、産業技術研究所が進める「統合化地下構造データベースの構築」をお手本にして進めてきました。産業技術研究所では「ボーリングデータ品質確認システム」を用いて、データベースに格納する前にデータの品質管理をしています。当センターの「電子納品」についても、確認プログラムのチェックを済ませていただき、担当者が楽にWebデータベースに格納できるようにしたいなと夢見ています。
現在、「電子納品」のWebデータベースは非公開となっています。ただし、同様なシステムを活用したデータベースは、当センターの公開HPで見ることができます。「遺跡の検索」から、報告書の「抄録データ」をご覧いただくと、遺構一覧や遺物一覧、実測図の画像データなどが紐づけられています。また報告書に至るまでの年報や、研究紀要の関連する論文まで、しつこいほど報告書に紐づけられています。ぜひ一度ご覧になってください。「遺跡アルバム」では、実測図と紐づけられているものもあります。小さな土器片が、実測図を見るとりっぱな土器になっているという感動が味わえます。
DXを進めると、情報へのアクセスが簡単になり、たくさんの人々の目に触れる機会が確実に増えます。収蔵庫の奥深くにしまい込まれた遺物たちも、デジタル化されていれば、簡単にみていただく事ができます。どうしても現物を実見しないといけないときだけ、ちょっと苦労すればよいということになります。遺物の移動も減らすことができますので、こわれやすい遺物の保存にもDXは大変有効ですね。