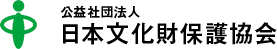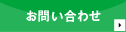高橋直崇(株式会社四門文化財)
1500万人がいなくなる時代に
2023年に日本で生まれた子供はおよそ76万人だそうです。
私は今50歳になるのですが、同じ年生まれは202万人いますので、半世紀で新生児は約三分の一に減ったことになります。
2023年生まれの76万人の多くが大学を卒業し働き始めるであろう2045年には、労働力の中核をなす22歳から65歳までの人口は現在から約1500万人、およそ23%減少することは確定しています。
文化財の仕事が選ばれるために
確実に文化財の現場からも人がいなくなりますが、2045年に単純に文化財関連で働く人数が23%減少することを意味しません。2045 年には全ての業種間で私世代の三分の一に減った若者の奪い合いの競争をするということです。恐らく全ての業種が従来の労働者数に依存しないための技術革新・改革・DXの推進に取り組んでいます。このような状況の中で、文化財関連の業務も他業種と比較し魅力的な仕事であると新しい世代に受け止められ、就職先として選んで貰えなければ持続的な文化財の保護と活用は実現し得えません。
ところが、未来の文化財調査の担い手の中心となる考古学専攻生の埋蔵文化財行政への就職率は、現在、学部卒業で5~10%、大学院修了で60~70%だそうです*1。文化財調査の職場は、理由は様々でしょうが現時点で既に魅力的な職場ではないのかも知れません。
さらにもう少し怖い話をします。
日本における一人当たり平均年間総実労働時間は、40年前の1985年に年間2,093時間だったものが、働き方改革の推進等によって2022年時点で1,607時間と約40年で486時間(約23%)減少しました*2。
日本の労働者人口は国勢調査の統計資料では1985年時点の6,005万人から2023年に6,930万人とおよそ900万人(約15%)増加しましたが、しかしその内実は、65歳以上の高齢者が626万人増加、外国人労働者は統計データの参照できる2008年~2022年で140万人増*3と、増加分の大半を占めています。
労働生産力、マンパワーを単純に「人数」×「時間」と定義した場合、日本全体で1985年から2022年にかけて既に11%減少していることになります。高齢者624万人、外国人労働者140万人以上を雇用に上乗せした下駄を履かせてもなお、もはやマンパワーではどうにもならない未来が何度か寝て起きた未来に待っています。文化財関連の業務で言えば、発掘作業員の確保が難しくなることが容易に予想されます。
文化財DXが目指すべき具体的な目標
文化財DXが推進宣言にあるように「未来に向けて持続可能な文化財の保存と活用の実現」を大きな目標にするのであれば、解決すべきもっと具体的で生々しい数値目標としては2045年に23%の労働者人口の減少への代替技術と仕事の方法の革新、そして半世紀前の三分の一に減少する22歳に選んで貰える魅力的な職場環境になる、という視点もきちんと盛り込む必要があるでしょう。
文化財の民間調査組織の中には、急激な会社の成長という経験をもつ会社がいくつかあります。弊社もここ十数年で事業規模が数倍に膨れ上がり、人員の補充・育成が追い付かない局面に立っています。この担い手不足という状況は、相対的に人口減少社会を先取りした形で社内体制の変革を強制的に迫ってきましたが、いよいよ社会全体で取り組む時代が来たようです。文化財DXは、単純に新しい方法を始めるのではなく、民間調査組織の担い手不足とその対応策の経験を持ち寄り、誰もが受け入れやすい、魅力的な職場環境への取り組みとしても考えていきたいと思います。
註
*1 文化庁の埋蔵文化財発掘調査体制等の整備充実に関する調査研究委員会による令和2年『埋蔵文化財専門職員の育成について』(報告)-資質能力の段階区分に応じた人材育成の在り方-
*2 独立行政法人労働政策研究・研修機構2024『データブック国際労働比較2024』
*3 藤坂浩司2023『人口減少が地域社会に与える影響 第5回「外国人労働者」「ぶぎんレポート№275」ぶぎん地域経済研究所