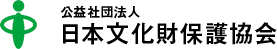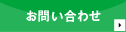坂本範基(ナカシャクリエイテブ株式会社)
「デジタルアーカイブ」や「デジタルミュージアム」。少し難しく聞こえるかもしれませんが、簡単に言えば、地域の貴重な文化財をデジタル化して、誰でもオンラインで楽しめるようにする取り組みのことです。この記事では、文化財デジタルアーカイブの背景や近年の動向を紹介しつつ、活用の可能性について考えてみたいと思います。
文化財アーカイブの背景
「デジタルアーカイブ」という言葉は和製英語*1で、1994年の国際会議で初めて使われ、その後1996年に推進協議会が結成されました。当時はインターネット黎明期で、1993年の一般公開や1995年のWindows95登場で普及が加速し、日本でも早くから文化財のデジタル化に注目が集まりました。
現在は国主導の取り組みが進み、2021年の「デジタル田園都市国家構想」や2022年の博物館法改正がアーカイブ化を後押ししています。代表的なプラットフォーム「ジャパンサーチ」は2020年に公開され、国会図書館など23機関・約2,100万件のデータを一元検索できます。このほか「文化遺産オンライン」など各地が参加する全国規模の共有基盤が整い、これまで、自分の地域だけでは難しかった広域的な活用が可能になり、地域文化の価値がさらに高まることが期待されています。
このような公開の取り組みやコンテンツに加え、資料をパブリックドメインやCCライセンスといったオープンなライセンスで提供する動きも広がっています。データの自由な利活用を促進している点が注目されます。
文化財デジタルアーカイブは 「未来への投資」
文化財デジタルアーカイブは、単なる「文化財をデジタル化して公開する技術」にとどまりません。各地で多彩なコンテンツが生まれ、現代の私たちが文化財に親しむきっかけをつくっています。これは、日本文化の保存・継承を見直し、その価値を再発見するとともに、過去と未来をつなぐ「文化への投資」です。
デジタル化によって、これまで研究者や地域住民に限られていた資料も、インターネットを通じて誰もがどこからでも閲覧可能になります。学校の教材や生涯学習の資料として活用が広がり、文化財にふれる機会が増えることで、私たち一人ひとりの歴史文化への理解が自然と深まっていきます。
新しい鑑賞体験が、文化財の魅力を引き出す
高精細な画像や、VR・メタバースなどの新しい技術によって、これまで気づかなかった文化財の魅力が見えてきます。たとえば、細かな筆づかいや建築装飾など細部の鑑賞、かつての風景の再現など、現地では体験できない「もう一つの文化財鑑賞」が可能になります。
こうした体験は、文化財に対する興味や関心を高めるだけでなく、「自分の地域にもこんな宝物があったんだ」と、地域への誇りにもつながります。
地域の魅力を世界へ――文化財を活かした新しい価値創出
デジタル化された文化財は、観光資源としても活用が進んでいます。地域の歴史や物語と組み合わせたコンテンツを作ることで、訪れる人に深い感動を与えられるようになります。
また、文化財を起点にした商品開発やイベント開催、海外への情報発信など、新たな産業の芽も育まれています。文化を守ることが、地域を元気にする力にもなっているのです。
文化財DXで、日本文化をもっと身近に、もっと魅力的に
このように、現在も広がり続ける文化財デジタルアーカイブには様々な可能性があります。文化財の本来の力――それは、人々の心を動かし、時代や国を超えてつながる力です。
これからのデジタル社会では、そうした文化財の力が、デジタル技術によって高められ、これまで考えられなかったような利活用の方法研究といった、新しい価値を生み出し続けるはずです。
*1 田良島哲「文化財の保存・活用とデジタル資源」(2019年5月21日)
https://cpcp.nich.go.jp/modules/rblog/1/2019/05/21/blog5/ (最終閲覧:2025年5月21日)
*2 国立国会図書館プレスリリース「ジャパンサーチ正式版の公開について」 (2020年8月25日)
https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2020/200825_02.html (最終閲覧:2025年5月21日)