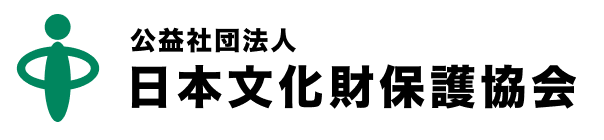事業活動
日本文化財保護協会では、内閣府から認定を受けた公益事業として、文化財保護を目的とした多様な事業を展開しています。
埋蔵文化財調査士 資格制度
埋蔵文化財調査従事者が、必要な専門知識や技能の向上を図り、もって埋蔵文化財調査の円滑化を促進することを目的として2007年(平成19年)に設立された制度で、日本文化財保護協会が制度の運営を行っています。
資格制度を構成する「埋蔵文化財調査士」と「埋蔵文化財調査士補」は、毎年1回実施される資格試験に合格し資格登録した人の埋蔵文化財調査に関する技量を説明する客観資料となるため、近年、埋蔵文化財発掘調査の発注に係る仕様書に、資格保有者の必要が特記されるなど、その重要度が増大しつつあります。
また、協会では、資格保有者の自主的な技能研鑽を支援するため、CPD制度(Continuing Professional Development=継続教育)を導入しており、資格取得後において、協会が主催する講習会の受講や論文発表等により決められたCPDポイントを獲得していくことで、5年毎に資格登録更新を行うことになっています。
考古検定
考古検定は、多くの皆さんに考古の面白さ、考古とは何かを知っていただき、各地域の歴史や文化に興味、関心を持ち、ひいては日本や世界の歴史、文化にも目を広げていただく目的で協会が2011年(平成23年)より毎年実施している検定制度です。
この検定は、誰もが取り組める「入門クラス」から、大学一般教養程度の「初級クラス」、大学考古学系学部の教養程度の「中級クラス」、大学の考古学系学部卒業程度の「上級クラス」、考古系大学院修了程度の「最上級クラス」まで難易度により5つのクラスが設定され、全て自宅のパソコンで受験ができるネット検定となっています。
協会では、考古検定の受験者向けに過去問題集を出版しており、現在「考古検定過去問題集 新版(第5~7回)」「考古検定過去問題集 第3版(第8~10回)」「考古検定過去問題集 第4版(第11~13回)」が当協会から販売されています。
セミナー、研修会、講習会
埋蔵文化財調査士 資格制度のCPD研修をはじめ、埋蔵文化財調査に関するセミナーから文化財保護に関するテーマまで、様々なプログラムを企画運営しています。
直近開催例
「文化財の危機管理」
「埋蔵文化財発掘調査における三次元計測技術の応用」
「発掘調査における安全管理と関連法規、救急講習」
「縄文原体を学ぶ(講義と実習)」
「縄文写真の基礎知識―より良い写真記録を残すためにー」
「火山灰編年学を基にした自然災害史調査法、火山災害遺跡の調査方法・事例」
ほか
調査研究
埋蔵文化財に係る民間調査機関の調査力向上を目的に、外部有識者からなる委員会に審査依頼し、毎年「優秀調査報告書」の表彰を実施しています。
また、民間調査機関に所属する発掘担当「企業内研究者」の考古学的研究発表の場として、2017年(平成29年)に日本文化財保護協会が監修する学術誌「紀要」を創刊し、年1回発行するとともに、全国の関係機関約1,300箇所へ送付寄贈しています。
協会独自の調査研究テーマとして、埋蔵文化財発掘現場におけるデジタル三次元技術の全面展開を主旨とする「日本文化財保護協会 DX(Digital Transformation)推進計画」に取組んでいます。
発掘調査受託
地震・風水害の復興支援や防災対策事業に係る埋蔵文化財発掘調査は調査範囲が広大であり、かつ期間も限定される場合が見受けられます。
このように公益性が高く大規模な発掘調査について、行政機関等の協力要請を受け、日本文化財保護協会が一括して受託して、会員企業の協力のもと、事業に取組んでいます。
協会では、円滑な事業進捗のため、最新のデジタル機器と計測手法を導入して、効率と品質の両立を図っています。
広報
民間調査機関の存在や実績を広く認知してもらう目的で、会員各社の最新事業概要や実績などをまとめた「要覧」を毎年発行し、全国の関係機関約1,300箇所へ送付寄贈しています。
また、毎年の協会活動をまとめた機関誌「飛天」を年1回発行し、公式SNS「X」にタイムリーな情報をポストするなど、広報活動に努めています。